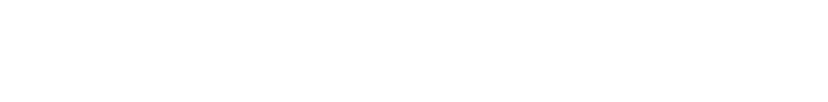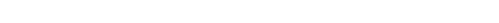コラム
【半世紀】券売機の進化と時代背景まとめ
2025年6月23日
町の中華屋や学食で目にしていた、懐かしの「食券」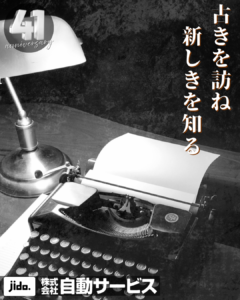
その一枚の紙の裏には、日本の社会とともに歩んできた“券売機”の進化があります。
そしてその進化を支えてきたのが、私たち自動サービスの「温故知新」の姿勢です。
今回は、昭和から令和にかけて、券売機がどのように時代背景とニーズに応えてきたのかをご紹介します。
🕰 昭和50年代(1970年代後半)〜昭和60年代前半(1980年代)
📌 時代背景
- 高度経済成長の終焉 → 安定成長期へ
- 学校・工場食堂の整備が進み、団体給食ニーズが拡大
- 外食産業の黎明期、セルフサービス文化の始まり
🔍 ニーズ
- 「人手に頼らずに食券を発行したい」
- 「現金の管理・レジ業務を省力化したい」
- 「大量利用に対応する仕組みが必要」
“省力化”の第一歩:スタンプ式食券と大量給食ニーズ
1970年代後半、高度経済成長を経て、世の中は安定成長期へ。
工場の社員食堂や学校の学食では、「短時間で大量の食事をさばく」仕組みが求められました。
そんな中登場したのが、「印判式券売機」。
スタンプをインクにつけて紙に押す方式で、紙の食券が「カチャン」と音を立てて出てくる仕組み。
シンプルながら、人手を減らし、現金管理もスムーズにできる画期的な存在でした。
📈 昭和60年代後半〜平成初期(1990年代)
📌 時代背景
- バブル景気のピークと崩壊(消費拡大とコスト圧縮の両立が求められる)
- ファストフード・ラーメン店など個人飲食店の増加
- POSレジの台頭と「データ経営」の兆し
🔍 ニーズ
- 「売上や人気メニューを数値で把握したい」
- 「食券の印字をもっと見やすくしたい」
- 「紙幣対応で単価の高い商品も扱いたい」
データ経営の萌芽:感熱式プリンタと売上集計機能の登場
1980年代後半、バブル景気の中で外食産業が盛り上がりを見せる一方、人件費の高騰が経営を圧迫。
そんな時代に登場したのが、感熱式プリンタ搭載の券売機でした。
インク不要で高速かつ静音。しかも、売上の集計やメニュー別の分析が可能に。
PCが普及する前の時代において、こうした機能はまさに「省力経営の革命」でした。
「売れているメニューは何か?」
「ピークタイムの回転率は?」
そんな経営判断のヒントを、券売機がデータで教えてくれるようになったのです。
💳 平成中期〜後期(2000年代)
📌 時代背景
- 少子高齢化・人材不足が加速
- 外国人観光客の増加(インバウンド)
- 生活スタイルの多様化とサービスの個別化が進行
🔍 ニーズ
- 「外国人にも対応できる券売機がほしい」
- 「紙幣やICカードなど多様な支払いに対応したい」
- 「高齢者でも使いやすい設計が求められる」
多機能化とユーザビリティの進化:紙幣・多言語・タッチパネル
2000年代に入り、外国人観光客の増加や少子高齢化が進む中、券売機にも変化が求められました。
・1,000円以上の紙幣に対応すること
・多言語表示によりインバウンドに対応
・高齢者にも見やすく、わかりやすいインターフェース
こうして登場したのが、タッチパネル式券売機。
写真付きメニューや音声案内も可能になり、券売機が“お店の受付係”としての役割を果たすようになります。
🌐 令和時代(2019年〜現在)
📌 時代背景
- キャッシュレス化とDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
- コロナ禍による非接触ニーズの高まり
- 労働力不足・物価高騰で“自動化”と“効率性”が必須に
🔍 ニーズ
- 「現場に行かずに売上や設定を管理したい」
- 「現金に頼らず、キャッシュレスで会計を完結したい」
- 「オペレーションをより自動化して人手不足を補いたい」
非接触・キャッシュレス時代のパートナーへ:クラウド×AIの進化
現代の飲食店を取り巻く課題は多岐にわたります。
人手不足、キャッシュレス対応、コロナ禍以降の非接触ニーズ…。
その解決に寄与しているのが、クラウド連携・AI機能を搭載した最新券売機です。
- 遠隔から売上や在庫の管理が可能に
- クレジットやQR決済に標準対応
- 客単価アップにつながる“おすすめ商品”表示
- インボイス制度やレシート出力にも柔軟対応
まさに、今の券売機は**「販売機械」から「経営ツール」へと進化**したと言えるでしょう。
🔧 そして、変わらぬ安心を—— 自動サービスのサポート体制
技術がどれだけ進化しても、現場では「安心して使えるか」「困ったときに頼れるか」が大切。
自動サービスでは、これまで蓄積してきたノウハウと「現場目線」でのご提案で、
最新機器の導入から運用・メンテナンスまで一貫してサポートしています。
オーナーが一杯のラーメンを心を込めて作ることに集中できるよう、
会計のやり取り、オススメ商品のアップセル、客単価アップまでも、券売機にお任せください。
券売機の導入は、今や気軽に始められる省力化の第一歩。
その後ろには、信頼できるサポート体制と、これからの時代に合った効率的な運営支援がついています。
🏷️ 食券の歴史は、社会の歴史
かつての印判式券売機に始まり、感熱式、タッチパネル、クラウド連携まで——
時代ごとのニーズに応じて進化してきた券売機の姿は、日本社会の変化とともに歩んできた歴史でもあります。
自動サービスは、これからも「古きをたずね、新しきを知る」視点を大切にし、
時代に求められる最適な券売機と、それを活かす未来へ『ビジネスを楽に』するお手伝いを続けて参ります。

※写真は(株)自動サービスが設置していた今はなきモデルの券売機。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/
「食券」の進化を追う:券売機と印字装置の知られざる歴史
2025年6月23日
昭和の町中華や学食で目にした、あの懐かしい「食券」。
その裏には、時代とともに進化してきた券売機の技術があります。
今回は、特に「印字装置」の変遷に注目して、券売機の歴史を振り返ってみましょう。
✨スタンプの音が響いた時代 ― 印判式の食券
1970年代から1980年代前半まで、食堂や学食などで使われていたのが「印判式券売機」。これは、ゴム印や金属スタンプをインクパッドに押し付けて、紙にメニューや金額を印字するものでした。
「カチャン」という音とともに出てくる、少しかすれたインクの券。それを持ってカウンターに差し出すのが、食事の始まり。今では見かけなくなりましたが、当時はそれが当たり前の光景でした。
ただしこの方式には課題も。スタンプが摩耗したり、インク切れで印字が薄くなったりと、メンテナンスの手間がかかっていました。
📈 革命を起こした感熱式プリンタの登場
そんな中、1980年代になると新たな印字技術が登場します。それが、**感熱式プリンタ(サーマルプリンタ)**です。
この方式は、感熱紙に熱を加えることで文字を印字するというもの。インクが不要で、印字速度も速く、非常に静か。紙詰まりや印字ミスも少ないため、業務用としての信頼性が飛躍的に高まりました。
最初は都市部や交通機関を中心に普及し、徐々に全国へと広がっていきます。
🚀 標準化と多機能化 ― 90年代から2000年代へ
1990年代後半になると、感熱式プリンタは事実上の業界標準に。食券・整理券・レシートにとどまらず、自治体の窓口や病院の順番札など、あらゆる場面に導入されました。
さらに2000年代には、QRコード印字や多言語対応、タッチパネル連動などの多機能化が進行。今では、券売機は「発券装置」以上の役割を担っています。
🏷️ 現在の主流技術と、残るレトロの味
現在の主流はもちろん感熱式プリンタ。メンテナンスが少なく、動作音も静か。コスト面でも優れており、多くの現場で重宝されています。
一方で、一部ではインパクトプリンタも健在。複写が必要な領収書などには、今も根強い需要があります。
そして今、かつてのスタンプ式券売機を懐かしむ声も多く、レトロブームの中で再評価される場面も増えています。
こうした変遷を振り返ると、券売機は技術だけでなく、日本の社会・文化と共に進化してきた存在であることがわかります。懐かしい印判式から、スマートな感熱プリンタまで、日本ならではの合理性と細やかな配慮が詰まっています。
🔧 そして今、「温故知新」の精神で進化を支える
私たち自動サービスは、創業以来のノウハウと、現代の技術を融合させ、最新機材の導入からアフターメンテナンスまでワンストップでご支援しています。
たとえば今の券売機は――
✅ タッチパネル式で誰でも使いやすく
✅ クレジットや電子マネー、QR決済対応でキャッシュレス化
✅ 売上データをリアルタイムでクラウド管理可能
✅ オススメ商品のアップセル表示で客単価アップにも貢献!
そして、会計ミスや注文の聞き間違いもゼロに。
「オーナーが一杯のラーメンに集中できる」
そんな店舗運営を、私たちが全力でサポートします。
👥 専門のコンサルタントによるサポート体制も万全です
導入前のご相談から、機種のご提案、設置、運用支援、故障対応まで、すべてを一貫してサポート。だからこそ「はじめての券売機」でも安心して導入できます。
🍜“人にやさしく、時代に沿った券売機を。”
これからも私たちは、「温故知新」の理念のもと、
お客様の現場に本当に合った省力化・効率化の仕組みを提供し続けてまいります。

※写真は(株)自動サービスが設置していた今はなきモデルの券売機。(1990年代)
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/
一杯のラーメンに、まっすぐ向き合える運営を。
2025年6月23日
私たち(株)自動サービスは、昭和51年に自動販売機での飲料販売からスタートし、昭和59年からは自動券売機の販売を九州全域に広げてまいりました。
当時は、まだ券売機といえば学生食堂に限られた存在。飲食店や公共施設で見かけるのはごく一部でした。それでも、私たちはこの機械が持つ「未来の可能性」に強く魅力を感じていました。
なぜなら、券売機は“ただの販売機”ではないからです。
券売機を導入することで、お店の方は「お釣りの間違い」や「聞き間違いによるオーダーミス」、「忙しさによるレジ混雑」といった人為的なストレスから解放されます。
そして何よりも――
一杯のラーメン、一皿の定食に心を込めることに集中できる環境が整うのです。
1980年代当時、まだパソコンも普及していない時代において、券売機に「売上集計機能」や「メニュー別の販売分析」機能がついたことは、まさに画期的な出来事でした。
「どの商品がよく売れているか?」「時間帯ごとの売れ筋は?」「無駄を減らせる仕入れは?」
そんな経営判断に必要なデータを、機械が“黙って”蓄積し、見せてくれるようになったのです。
現代では、少子高齢化や人手不足が深刻な問題となっています。
「人が足りないから休業せざるを得ない」
「スタッフが辞めてしまい、営業に支障が出た」
そんなお悩みをよく耳にします。
でも、もし券売機をうまく活用すれば、最小限の人数で、効率的かつ丁寧な接客・調理が可能になる。
これは40年以上前と変わらない、そして今だからこそさらに価値が高まっている「省力化の力」です。
券売機は“客単価アップ”にも貢献します。
最近の券売機は、売れ筋商品の表示やセットメニューの提案など、「オススメ商品のアップセル」機能も充実しています。
「あと一品」「大盛り変更」など、店頭では声かけしにくい提案も、券売機が自然に行ってくれる。
客単価アップを、“無理なく”実現できる時代になっているのです。
もちろん、支払いのやり取りも自動化されるため、ミスもゼロに。
現金・QR決済・ICカードなど、幅広い支払い方法にも対応できます。
店内オペレーションは、券売機にお任せ。
オーナーさんが一杯のラーメンに心を込めるために、
注文・会計・売上集計といった「裏方の仕事」は、券売機がしっかり担います。
私たちはこれまで培ってきた導入実績と運用ノウハウを活かし、
「券売機でどこまでできるか?」「何を省けるか?」を見極めながら、最適な運営スタイルをご提案。
専任のコンサルタントが、店舗ごとの課題やオペレーションに合わせて、導入から運用まで丁寧にサポートいたします。
信頼できるサポート体制と共に、 気軽に始められる省力化機器の導入と、 より効率的な店舗運営の実現というかたちで、 これからも現場の皆さまを応援してまいります。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/
実はスゴかった!?1980年代の券売機がもたらした“データ経営”の始まり
2025年6月23日
■ パソコンが珍しかった時代に、券売機が「経営の味方」に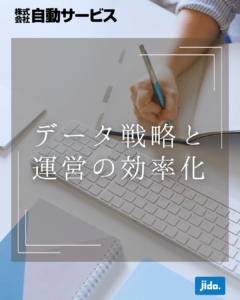
今では当たり前のように、スマホやパソコンで売上管理やメニュー分析ができる時代ですが、
それが当たり前ではなかった時代に、弊社は券売機の販売を開始いたしました。――1980年代前半(昭和59年前後)
実はすでに“経営に役立つデータ”を提供してくれていた券売機があったんです。
当時は、パソコンは一部の企業や大学などでしか使われておらず、
「数字をまとめる」「集計する」といえば、手書きの帳簿や電卓が主流。
そんな時代に、券売機が自動で売上を集計したり、人気メニューを分析したりできることは、まさに画期的でした。
■ 注文を“売る”だけじゃない。経営判断にもつながる券売機
当時の一部の高機能券売機では、
・何時に何が売れたか
・どの商品が一番出ているか
・どの時間帯にピークがあるか
といった販売データを記録・集計する機能が搭載されていました。
これにより、店舗経営者は「売れている商品」や「仕込み量」「人員配置」など、
“なんとなく”ではなく“数字に基づいて”判断できるようになったのです。
現代風に言えば、これはまさに「POSレジ」や「BIツール(ビジネスインテリジェンス)」の原型とも言えます。
■ 人手不足・経費削減・スピード経営――現代にも通じる課題に
そして面白いのが、この時代に抱えていた課題が、今の時代にも通じているという点です。
たとえば、
- 人手不足で店舗運営が大変
- 経費を見直したいけど、何から削ればいいかわからない
- 売上データを活用したいけど、難しそうで手がつけられない
こんなお悩み、現代でもよく耳にしますよね?
だからこそ、今あらためて「シンプルで、誰でも扱いやすい券売機」が注目されているんです。
特別な知識や端末がなくても、**“ボタン一つで売上が見える”**という仕組みは、今の時代にもマッチしています。
■ 温故知新――昔の技術に、今のヒントがある
昭和の時代に生まれた券売機ですが、その本質は今も変わりません。
それは、「人の負担を減らし、経営に余裕をつくる」ということ。
最新のITツールも便利ですが、
「誰でも使えて、すぐに成果が見える」仕組みとして、
券売機というツールは**今も変わらず、“経営の味方”**であり続けています。
創業から今日まで、私たちは“温故知新”の精神を大切に、
「昔の良い知恵」を生かしながら、今の現場に合った形でご提案を続けています。
■ 最後に
時代が変わっても、現場の悩みは意外と変わらないもの。
だからこそ、券売機の持つシンプルな強さと、データによる気づきを、
これからも皆さまの経営に活かしていただければ幸いです。
Q:どんな機種が今の現場に最適なのか?
Q:今よりも効率的なオペレーションにしたい!
Q:今の券売機では、イマイチ便利さを感じない。
そんな気になる点を、お気軽にお問い合わせください!
営業担当が親身にヒアリングと無料相談に対応させていただきます。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/
日本の券売機の歴史と、いま再び求められる理由
2025年6月23日
■ はじまりは鉄道から。券売機の登場
日本で最初に「券売機」が登場したのは、実は 駅の切符販売が最初でした。
1950年代、国鉄(今のJR)が改札業務の負担軽減を目的に、ボタン式の切符販売機を導入したのが始まりです。
最初の頃は、「ボタンが多くて難しそう」とか「人のほうが安心」といった声もありましたが、駅の利用者がどんどん増える中で、スムーズな切符購入を実現する便利な機械として広まりました。
■ 昭和50年代〜80年代:飲食業界にも広がる
やがて技術の進歩とともに、飲食店にも券売機が導入され始めたのが昭和50年代〜60年代。
学生食堂をはじめとする、社員食堂、ラーメン店などで見かけるようになりました。
この頃の背景には、まさに「省力化」や「人手不足」の波がありました。
高度成長期を経て、人件費の高騰や労働時間短縮の要請が社会全体に広がっていた時代です。
そんな中、券売機は「未来的で便利な機械」として評価されていきます。
お店にとっては人件費が抑えられ、注文ミスも減り、スムーズなオペレーションが可能に。
まさに、当時の“働き方改革”の先駆けと言える存在でした。
■ 平成〜令和:一度は減少、でも今また注目される理由
実は一時期、券売機の数はやや減少傾向にありました。
キャッシュレス決済の普及や、スマホ注文アプリの登場など、デジタル化が急速に進んだからです。
ですが、ここにきて再び「券売機」が見直されつつあります。
その理由のひとつが、人手不足の深刻化。
特に飲食業界やサービス業では、スタッフの確保がますます難しくなっています。
また、近年はコロナ禍の影響もあり、
「非接触」「対面を減らす」ことが重要視されるようになりました。
そんな時、シンプルで誰でも使える「ユニバーサルデザイン」である券売機の存在は、逆に安心感を与える武器になっています。
■ これからの券売機は、「人にやさしいテクノロジー」
最近の券売機は、多言語対応・キャッシュレス・大型画面・音声ガイドなど、どんどん進化しています。
けれど、どんなに高性能になっても、その目的は変わりません。
それは、「人に代わって、人を助ける」ということ。
長時間のレジ対応に悩むお店や、スタッフが少ない店舗でも、
券売機があれば負担を軽くしてくれる存在になります。
また、高齢者でも使いやすいインターフェースや、操作ミスを防ぐ設計など、ユーザーに寄り添った進化も進んでいます。
■ まとめ:時代はめぐる。だからこそ「原点」が強みになる
券売機は、日本の効率化社会の中で生まれ育った、まさに働く人の味方ともいえる存在です。
デジタル化やIT化が進む今だからこそ、「誰にでもわかりやすく・確実に・便利に」使える券売機の価値が、改めて見直されています。
これからの時代も、“原点を大切にしながら新しさを取り入れる”。
まさに弊社が掲げる温故知新の精神で、全く新しいコンセプトのセルフPOS会計機の開発に至りました。
POSのノウハウを取り入れた全く新しいコンセプトのセルフPOS会計機 【PSZ1シリーズ】

詳しくは弊社HP製品情報より https://jido.co.jp/products/ticketing/psz1/
これからも、時代のニーズに合わせて券売機を進化するべく、培われた経験と、顧客目線でご支援をさせていただく姿勢を大切に、企業努力を続けて参ります。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/
創業ストーリー
2025年6月23日
弊社の原点は、昭和51年に代表者が個人事業として始めた自動販売機による飲料販売にあります。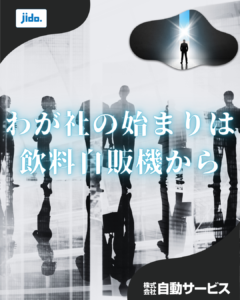
それから8年後の昭和59年、株式会社自動サービスを設立し、東洋通信機株式会社(現・NECマグナスコミュニケーションズ株式会社)製の自動券売機の販売を本格的に開始いたしました。
当時の「券売機」は、まだ学生食堂に限られた設置が主流で、現在のように飲食店や公共施設に広く普及している状況ではありませんでした。
この頃の日本社会は、高度経済成長期から安定成長期へと移行する時代背景にあり、
社会全体で省力化・効率化の動きが急速に進んでいる頃です。
何かと人の仕事を肩代わりしてくれる機械は注目を集める存在と言えました。
たとえば:
・工場における産業用ロボットの導入
・オフィスでのワープロ・ファクシミリ・コピー機の普及
・生活家電の自動化・高性能化の進展
など、さまざまな分野で「人手に頼らない仕組み」が求められ始めた時期であり、
特に、バブル経済の前段階に差し掛かる中で、
人手不足や労働時間の短縮といった社会的課題が背景にはありました。
そこで、まさに券売機という存在が地域の生産性向上と効率化に寄与できると考えたのです。
弊社は券売機を地域密着型の営業活動を通じて、お客様が安心して運用できるよう、
メンテナンスを担う技術部門を設置し、アフターサポート体制を強化して広めてまいりました。
地域に根差した営業活動と運用のメンテナンス支援を展開していく中で、
券売機は「未来的で便利な機械」として注目され、九州全域から山口・中国地方まで導入が進み始めました。
こうした時代の流れの中で、
券売機をはじめ、レジやシステムなどの省力化機器の提案と運用支援を通じて、
九州全域の効率化社会の進展を支える一翼を担ってきたと自負しております。
これまで、個人店様から企業様まで幅広いお客様より、
「地域社会の効率化と現場の未来を支える、自動化社会のパートナー」として、
高い評価をいただいてまいりました。
創業以来積み重ねてきた現場の知恵と経験を大切にしながら、
時代の変化を柔軟に捉え、
お客様一人ひとりの現場に寄り添い、
新しい価値を創造していく――
これこそが、私たち自動サービスの掲げる『温故知新』の精神です。

※写真は昭和63年ごろの初代社屋完成当初の写真。
現在は3代目社屋を福岡県糟屋郡新宮町に構える。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/