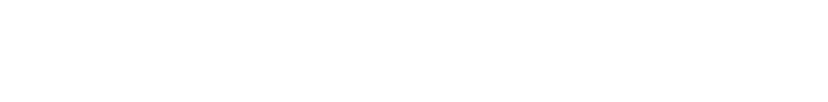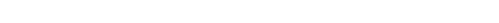昭和の町中華や学食で目にした、あの懐かしい「食券」。
その裏には、時代とともに進化してきた券売機の技術があります。
今回は、特に「印字装置」の変遷に注目して、券売機の歴史を振り返ってみましょう。
✨スタンプの音が響いた時代 ― 印判式の食券
1970年代から1980年代前半まで、食堂や学食などで使われていたのが「印判式券売機」。これは、ゴム印や金属スタンプをインクパッドに押し付けて、紙にメニューや金額を印字するものでした。
「カチャン」という音とともに出てくる、少しかすれたインクの券。それを持ってカウンターに差し出すのが、食事の始まり。今では見かけなくなりましたが、当時はそれが当たり前の光景でした。
ただしこの方式には課題も。スタンプが摩耗したり、インク切れで印字が薄くなったりと、メンテナンスの手間がかかっていました。
📈 革命を起こした感熱式プリンタの登場
そんな中、1980年代になると新たな印字技術が登場します。それが、**感熱式プリンタ(サーマルプリンタ)**です。
この方式は、感熱紙に熱を加えることで文字を印字するというもの。インクが不要で、印字速度も速く、非常に静か。紙詰まりや印字ミスも少ないため、業務用としての信頼性が飛躍的に高まりました。
最初は都市部や交通機関を中心に普及し、徐々に全国へと広がっていきます。
🚀 標準化と多機能化 ― 90年代から2000年代へ
1990年代後半になると、感熱式プリンタは事実上の業界標準に。食券・整理券・レシートにとどまらず、自治体の窓口や病院の順番札など、あらゆる場面に導入されました。
さらに2000年代には、QRコード印字や多言語対応、タッチパネル連動などの多機能化が進行。今では、券売機は「発券装置」以上の役割を担っています。
🏷️ 現在の主流技術と、残るレトロの味
現在の主流はもちろん感熱式プリンタ。メンテナンスが少なく、動作音も静か。コスト面でも優れており、多くの現場で重宝されています。
一方で、一部ではインパクトプリンタも健在。複写が必要な領収書などには、今も根強い需要があります。
そして今、かつてのスタンプ式券売機を懐かしむ声も多く、レトロブームの中で再評価される場面も増えています。
こうした変遷を振り返ると、券売機は技術だけでなく、日本の社会・文化と共に進化してきた存在であることがわかります。懐かしい印判式から、スマートな感熱プリンタまで、日本ならではの合理性と細やかな配慮が詰まっています。
🔧 そして今、「温故知新」の精神で進化を支える
私たち自動サービスは、創業以来のノウハウと、現代の技術を融合させ、最新機材の導入からアフターメンテナンスまでワンストップでご支援しています。
たとえば今の券売機は――
✅ タッチパネル式で誰でも使いやすく
✅ クレジットや電子マネー、QR決済対応でキャッシュレス化
✅ 売上データをリアルタイムでクラウド管理可能
✅ オススメ商品のアップセル表示で客単価アップにも貢献!
そして、会計ミスや注文の聞き間違いもゼロに。
「オーナーが一杯のラーメンに集中できる」
そんな店舗運営を、私たちが全力でサポートします。
👥 専門のコンサルタントによるサポート体制も万全です
導入前のご相談から、機種のご提案、設置、運用支援、故障対応まで、すべてを一貫してサポート。だからこそ「はじめての券売機」でも安心して導入できます。
🍜“人にやさしく、時代に沿った券売機を。”
これからも私たちは、「温故知新」の理念のもと、
お客様の現場に本当に合った省力化・効率化の仕組みを提供し続けてまいります。

※写真は(株)自動サービスが設置していた今はなきモデルの券売機。(1990年代)
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/