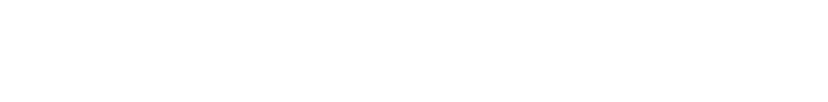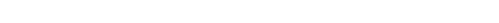■ はじまりは鉄道から。券売機の登場
日本で最初に「券売機」が登場したのは、実は 駅の切符販売が最初でした。
1950年代、国鉄(今のJR)が改札業務の負担軽減を目的に、ボタン式の切符販売機を導入したのが始まりです。
最初の頃は、「ボタンが多くて難しそう」とか「人のほうが安心」といった声もありましたが、駅の利用者がどんどん増える中で、スムーズな切符購入を実現する便利な機械として広まりました。
■ 昭和50年代〜80年代:飲食業界にも広がる
やがて技術の進歩とともに、飲食店にも券売機が導入され始めたのが昭和50年代〜60年代。
学生食堂をはじめとする、社員食堂、ラーメン店などで見かけるようになりました。
この頃の背景には、まさに「省力化」や「人手不足」の波がありました。
高度成長期を経て、人件費の高騰や労働時間短縮の要請が社会全体に広がっていた時代です。
そんな中、券売機は「未来的で便利な機械」として評価されていきます。
お店にとっては人件費が抑えられ、注文ミスも減り、スムーズなオペレーションが可能に。
まさに、当時の“働き方改革”の先駆けと言える存在でした。
■ 平成〜令和:一度は減少、でも今また注目される理由
実は一時期、券売機の数はやや減少傾向にありました。
キャッシュレス決済の普及や、スマホ注文アプリの登場など、デジタル化が急速に進んだからです。
ですが、ここにきて再び「券売機」が見直されつつあります。
その理由のひとつが、人手不足の深刻化。
特に飲食業界やサービス業では、スタッフの確保がますます難しくなっています。
また、近年はコロナ禍の影響もあり、
「非接触」「対面を減らす」ことが重要視されるようになりました。
そんな時、シンプルで誰でも使える「ユニバーサルデザイン」である券売機の存在は、逆に安心感を与える武器になっています。
■ これからの券売機は、「人にやさしいテクノロジー」
最近の券売機は、多言語対応・キャッシュレス・大型画面・音声ガイドなど、どんどん進化しています。
けれど、どんなに高性能になっても、その目的は変わりません。
それは、「人に代わって、人を助ける」ということ。
長時間のレジ対応に悩むお店や、スタッフが少ない店舗でも、
券売機があれば負担を軽くしてくれる存在になります。
また、高齢者でも使いやすいインターフェースや、操作ミスを防ぐ設計など、ユーザーに寄り添った進化も進んでいます。
■ まとめ:時代はめぐる。だからこそ「原点」が強みになる
券売機は、日本の効率化社会の中で生まれ育った、まさに働く人の味方ともいえる存在です。
デジタル化やIT化が進む今だからこそ、「誰にでもわかりやすく・確実に・便利に」使える券売機の価値が、改めて見直されています。
これからの時代も、“原点を大切にしながら新しさを取り入れる”。
まさに弊社が掲げる温故知新の精神で、全く新しいコンセプトのセルフPOS会計機の開発に至りました。
POSのノウハウを取り入れた全く新しいコンセプトのセルフPOS会計機 【PSZ1シリーズ】

詳しくは弊社HP製品情報より https://jido.co.jp/products/ticketing/psz1/
これからも、時代のニーズに合わせて券売機を進化するべく、培われた経験と、顧客目線でご支援をさせていただく姿勢を大切に、企業努力を続けて参ります。
お問い合わせ・資料請求は弊社HPより https://jido.co.jp/contact/